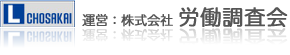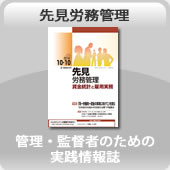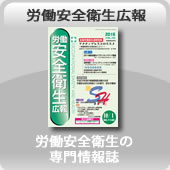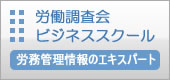特集改正年金法④(子に係る加算等・脱退一時金の見直し)
老齢基礎年金に子の加算を創設し一律28万1,700円(2024年度価格)を加算
前回(本誌第2212号(2025年8月11日付け))の特集「改正年金法③(厚生年金保険の標準報酬月額の上限の段階的引上げ、将来の基礎年金の給付水準の底上げ、私的年金制度の見直し)」では、2025年6月13日に可決・成立し、同年6月20日に公布された「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」(以下「改正法」という)の、I「働き方に中立的で、ライフスタイルの多様化等を踏まえた制度を構築するとともに、高齢期における生活の安定及び所得再分配機能の強化を図るための公的年金制度の見直し」の中の、4「厚生年金保険の標準報酬月額の上限の段階的引上げ」、5「将来の基礎年金の給付水準の底上げ」、II「私的年金制度の見直し」について紹介した。 改正法III「その他」の子に係る加算等の見直しでは、「老齢基礎年金に子の加算を創設し、老齢基礎年金の受給権者がその権利を取得した当時、当該受給権者によって生計を維持されていた子がいるときは、その子1人につきそれぞれ26万9,600円に改定率(1.045)を乗じた額(28万1,700円(2024年度価格))を加算する」としている。 また、障害基礎年金の子の加算(現行は、子1・2人目までは各23万4,800円(2024年度価格)、3人目以降は各7万8,300円(2024年度価格))を拡充し、「当該障害基礎年金の受給権者によって生計を維持されている子1人につき、それぞれ26万9,600円に改定率(1.045)を乗じた額(28万1,700円(2024年度価格))を加算する」とされている。 一方、老齢厚生年金に加算する加給年金(現行における子の加算額は障害基礎年金と同じ。65歳未満の配偶者に係る加算額は、23万4,800円(2024年度価格))について、「当該老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時、当該受給権者によって生計を維持されていた子1人につき、それぞれ26万9,600円に改定率(1.045)を乗じた額(28万1,700円(2024年度価格))を加算するとともに、65歳未満の配偶者に係る加算額を、20万2,200円に改定率(1.045)を乗じた額(21万1,300円(2024年度価格))とする」としている。 他方、脱退一時金制度について、現行では、再入国許可付き出国をした場合でも脱退一時金の受給は可能となっているが、将来の年金受給に結びつけやすくする観点から、「再入国の許可を受けて日本を出国した者は、当該再入国の許可を受けている間、脱退一時金の請求ができないものとする」とされている。また、支給上限については、現行の5年から「8年に引き上げる(政令で措置予定)」としている。
News
- (厚労省「第70回 中央最低賃金審議会」を開催) 政府目標は今後5年度で445円引上げ
- (雇用保険の基本手当日額の変更) 令和6年度の平均給与額・最賃日額に伴い引上げ
- (政府・外国人共生社会推進室設置) 内閣官房に省庁横断で外国人政策担う司令塔組織
- (電離放射線障害業務上外検討会) 福島第一原発事故の作業従事者15件目の労災認定
- (北海道国家戦略特別区域)厚労省が8ヵ所目の雇用労働相談センターを設置
特集
労働安全衛生法等の改正③(最終回)
高年齢労働者の労働災害防止の推進
令和8年度から高年齢労働者の労働災害防止措置が事業者の努力義務に
特集トピックス
令和6年度 過労死等の労災補償状況
~脳・心臓疾患に関する事案~
業種別では「運輸業,郵便業」が 請求件数・支給決定件数ともに最多
シリーズクローズアップ 新法律問題
File25「事業譲渡・合併・会社分割の労働者対応」
労働契約の承継に関して公序良俗違反や法人格否認の法理が適用される例も
シリーズ労働スクランブル
~働く側の人・組織からの声・意見~
第494回
収入格差拡大した4割、階層意識は「下」
~連合総研の「収入格差に関する認識と階層意識」を読み解く~
労務相談室
- 労務一般6ヵ月間の紹介予定派遣後に採用する者/採用時に年休付与必要か
- 賃金関係新卒に7年・中途は4年の住宅手当支給/異なる取扱いに問題は
- 賃金関係永年勤続表彰の算定の対象期間/パートの期間含めてないが
【労働基準広報】読者会員専用サイトでは以上の記事の全文(PDF)を閲覧できます。