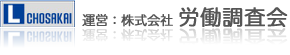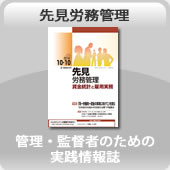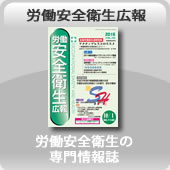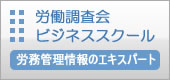特集改正年金法⑤ 最終回(障害年金等の直近1年要件の延長等)
遺族厚生年金受給権者で当該年金の請求してない者は老齢厚生年金の繰下げ可能
本誌第2213号(2025年8月21日付け)の特集I「改正年金法④(子に係る加算等・脱退一時金の見直し)」では、2025年6月13日に可決・成立し、同年6月20日に公布された、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」(以下「改正法」という)III「その他」の、「子に係る加算等の見直し」、「脱退一時金制度の見直し」について紹介した。 III「その他」では、これらのほか、障害年金等の直近1年要件の延長があり、障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)の支給要件には、保険料納付要件(初診日の前日において、当該初診日がある月の2ヵ月前までに国民年金の被保険者期間があり、当該被保険者期間に、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あること)の特例が設けられている。改正前は、初診日が令和8年3月末日までにあり、「当該初診日に65歳未満で、当該初診日の前日において、初診日がある月の2ヵ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと」を満たせば、保険料納付要件を満たすものとされていた。改正法により、「令和18年4月1日前に初診日がある場合も引き続き適用できるよう、時限措置の10年延長を行う」としている(令和7年6月20日施行済)。 また、国民年金の納付猶予制度について、改正前は、令和12年6月までに、20歳以上50歳未満の第1号被保険者等及び配偶者の前年の所得(1月から6月までの保険料については、前々年の所得)が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予される。改正法では、この納付猶予制度の期限を5年間延長し「令和17年6月までとする」としている(令和7年6月20日施行済)。 一方、離婚時分割の請求期限の伸長では、現行における離婚時分割(婚姻期間に係る厚生年金保険の計算の元となる標準報酬を当事者間で分割する制度)の請求は、原則として離婚等をした日の翌日から起算して2年以内とされている。改正法では、民法における離婚時の財産分与請求権の除斥期間が2年から5年に伸長されることに伴い、離婚時分割の請求期限についても「5年に伸長する」としている。 また、遺族厚生年金受給権者の老齢年金の繰下げの許容は、現行において、老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給権者で、65歳到達時、または65歳到達時から66歳到達時までに遺族厚生年金の受給権者となった者は、当該老齢年金の繰下げを行うことはできない。改正法では、「遺族厚生年金受給権者も、老齢基礎年金、老齢厚生年金(当該遺族厚生年金の請求を行っていない場合に限る)の繰下げを可能とする」とされている。
News
- (労働条件分科会・労働基準関係法制の議論が一巡) 年休取得8割出勤要件の要否など検討
- (労基法等関連届出等の電子申請) 就業規則(変更)届の電子申請利用率52%に上昇
- (7年3月 新卒内定取消し状況) 入職時期繰下げ状況は2事業所で合計93人に増加
- (10月1日からの「教育訓練給付」) 新たに特定一般200講座専門実践162講座を指定
- (令和6年 賃金不払関係の監督指導) 不払件数・労働者数・金額いずれも前年比増加に
- (厚生年金保険等の令和6年度収支決算) 決算結了後の年金積立金過去最高の260兆757億円
- (令和6年「労働安全衛生調査」) メンヘル対策実施は50人以上の事業所で94.3%に
- (若年層仕事と育児の両立意識調査) 育休取得について72.2%が男女は関係ないと回答
- (令和6年の就業医療関係者)保健師、看護師、はり師等が調査開始以降最多に
- (令和7年度 年次経済財政報告) スポットワークの総労働時間は無視できない規模
特集ひと はなし
より良い労働条件を提示して人を惹きつけておくことが社会全体の底上げに
◆山田雅彦 厚生労働審議官に聞く
シリーズクローズアップ 新法律問題
File26「競業避止義務を定める条項の有効性」
場所的限定や期間、代償措置等の内容により条項が無効となり得る
シリーズ行政案内
令和7年度 全国労働衛生週間実施要綱
シリーズ労働スクランブル
~働く側の人・組織からの声・意見~
第496回
秋の余暇は物価高で国内観光旅行がトップ
~日本生産性本部余暇創研の「レジャー白書2025」速報版から~
労務相談室
- 育児・介護休業法所定外労働免除と時間外労働の制限/同時に請求できるか
- 紛争・訴訟引き抜き行為を行わない旨の誓約書の提出を拒否/禁止の効力は
- 障害者雇用率が来年7月の引上げで2.7%に/身体障害者限定採用は
【労働基準広報】読者会員専用サイトでは以上の記事の全文(PDF)を閲覧できます。